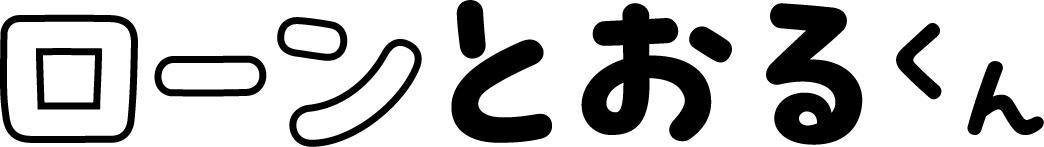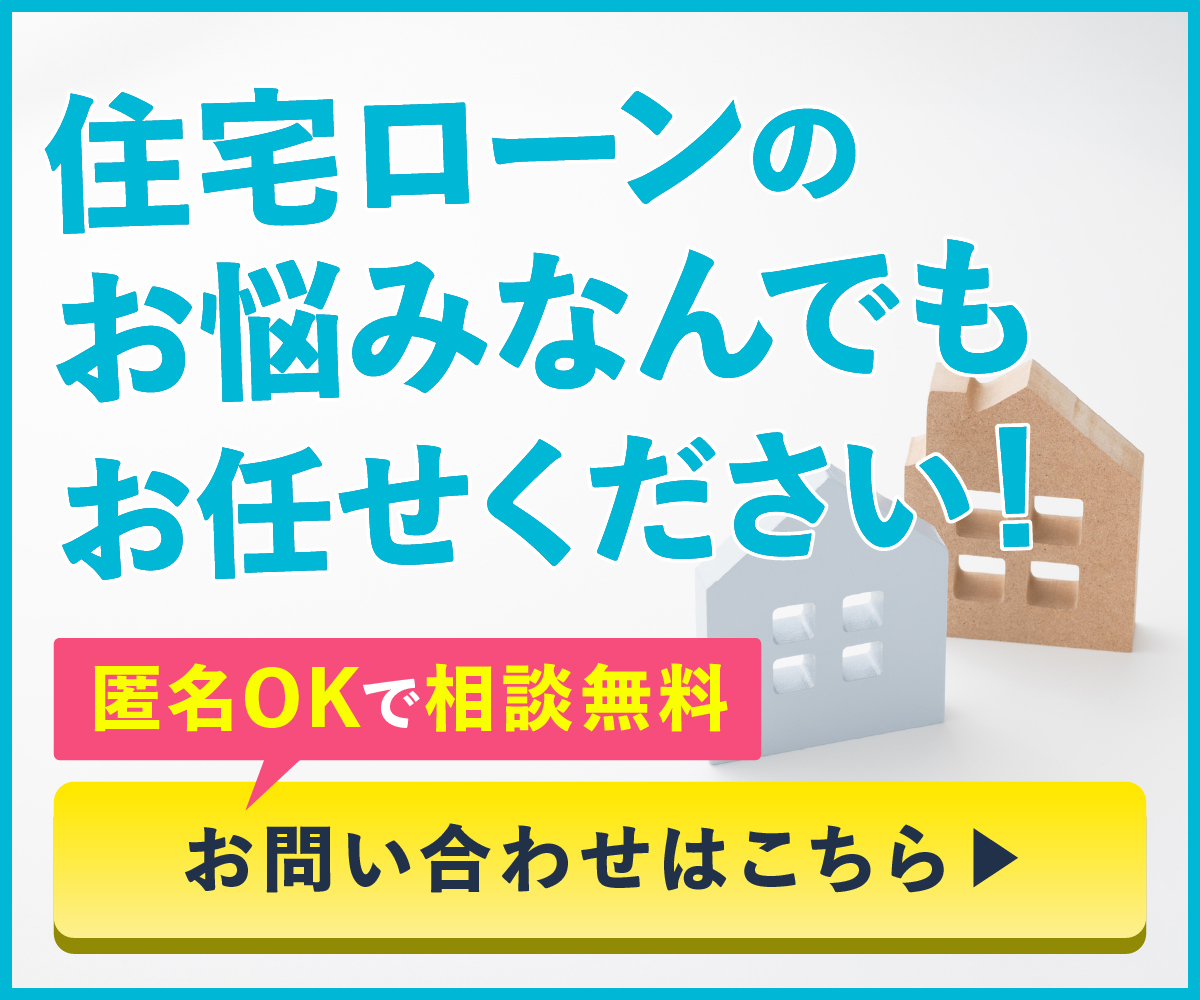株式投資に興味があるけど、まとまった資金がない…そんな方に注目されているのが「ミニ株」です。
しかし、実はミニ株には「おすすめしない」という声も多く聞かれます。一体なぜでしょうか?

編集部
今回は、ミニ株がおすすめできない理由から、初心者が陥りやすい失敗パターン、そして代替案となる投資方法まで詳しく解説していきます。
これから投資を始めようと考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
ミニ株とは?

投資を始めたいけど「まとまった資金がない」「いきなり大きな金額は怖い」という方に人気のミニ株。

編集部
まずは、このミニ株がどんな仕組みなのか、通常の株式投資とどう違うのかを詳しく見ていきましょう。
基本的なミニ株の仕組み
ミニ株とは、通常の株式投資では100株や1,000株といった単元株数でしか購入できない株式を、1株から購入できるサービスのことです。
例えば、通常なら100株で50万円必要な株式でも、ミニ株なら1株5,000円から購入できるというわけです。
これにより、資金が少ない投資初心者でも気軽に株式投資を始められるのが最大の特徴となっています。
現在では楽天証券の「かぶミニ®」、SBI証券の「S株」、マネックス証券の「ワン株」など、多くの証券会社がミニ株サービスを提供しています。
スマホアプリから簡単に取引できることもあって、特に若い世代から人気を集めているのです。
株式投資との違い
通常の株式投資とミニ株の違いは、単純に購入単位の違いだけではありません。
実は、取引方法や権利関係においても大きな違いがあります。
まず取引時間について。
通常の株式投資では市場が開いている間はリアルタイムで取引できますが、ミニ株の多くは1日数回の決められた時間にまとめて取引が行われます。

編集部
つまり、「今すぐ買いたい!」と思ってもすぐには買えないのです。
また、株主としての権利にも違いがあります。
通常の株式投資では議決権や株主優待を受ける権利がありますが、ミニ株では議決権は基本的にありません。
株主優待についても、必要な株数に達していなければ受けられないケースがほとんどです。
こうした違いを理解せずにミニ株を始めてしまうと、「思っていたのと違った…」という結果になってしまうことが多いのが現状です。
ミニ株がおすすめできない理由

少額から始められて魅力的に見えるミニ株ですが、実は多くの投資家が「おすすめしない」と口を揃えます。
その背景には、投資パフォーマンスに直接影響する深刻な問題があるのです。

編集部
ここでは、その具体的な理由を一つずつ詳しく解説していきます。
売買手数料が割高になるから
ミニ株最大のデメリットとして挙げられるのが、手数料の高さです。
これは本当に無視できない問題です。
例えば、auカブコム証券のプチ株では、手数料が約定価格の0.55%(最低52円)かかります。
仮に1万円分の株を購入した場合、手数料は55円。これは投資額の0.55%に相当します。
一方、通常の株式取引では、SBI証券なら10万円以下の取引でも手数料は99円。
100株で10万円の株を購入する場合、手数料率は約0.1%程度になります。
つまり、同じ投資額でも、ミニ株の方が5倍以上の手数料率になってしまうということです。
これでは、せっかく投資で利益が出ても、手数料で相殺されてしまう可能性が高くなります。
特に頻繁に売買を繰り返すような投資スタイルの場合、手数料だけでかなりの負担になってしまいます。

編集部
投資の基本は「コストを抑えること」ですから、この点だけでもミニ株は不利と言わざるを得ません。
取引のタイミングを自由に選べないから
株式投資の醍醐味の一つは、市場の動きを見ながらリアルタイムで売買タイミングを判断できることです。
しかし、ミニ株ではこの自由度が大幅に制限されてしまいます。
多くの証券会社では、ミニ株の取引は1日2〜3回の決められた時間にまとめて処理されます。
例えば「朝9時の寄り付き価格」「午後3時の終値価格」といった具合です。
これでは、「株価が下がったタイミングで買いたい」「急騰したから利益確定したい」といった機動的な投資ができません。
また、指値注文(希望する価格での注文)ができない証券会社も多く、成行注文(その時の市場価格での注文)しか選択できないケースがほとんど。
これでは、思った以上に高い価格で買ってしまったり、安い価格で売ってしまったりするリスクが高まります。
株主優待や配当のメリットが限定的
株式投資の楽しみの一つが株主優待です。
企業から送られてくる商品券や割引券、自社製品などは、投資の醍醐味と言えるでしょう。
しかし、ミニ株ではこのメリットを十分に享受できません。
株主優待を受けるためには、通常「100株以上保有」といった条件があります。
ミニ株で少しずつ積み立てても、この条件を満たすまでには相当な時間とコストがかかってしまいます。
配当についても同様です。
確かにミニ株でも配当は受け取れますが、保有株数が少なければ当然配当額も少なくなります。
年間数十円から数百円程度の配当のために、高い手数料を払って投資するのは効率的とは言えません。
例えば、配当利回り3%の株を1万円分(10株)保有しても、年間配当は300円程度。
ここから税金が引かれるので、実際の手取りは240円程度になってしまいます。

編集部
売買手数料を考慮すると、実質的にはマイナスになってしまうケースも珍しくありません。
流動性の低さによるリスク
流動性とは、その株がどれだけ活発に取引されているかを示す指標です。
ミニ株は通常の株式取引と比べて流動性が低く、これがリスクとなることがあります。
ミニ株は証券会社が一旦買い取った後に投資家に売るという仕組みのため、売りたい時にすぐに売れない可能性があります。
特に取引量の少ない銘柄の場合、希望する価格で売買できないリスクが高まります。
また、市場が急変した際に、迅速な対応ができないという問題もあります。
株価が急落している時に損切りをしたくても、次の取引時間まで待たなければならないため、損失が拡大してしまう可能性があります。
分散投資の効果が薄いから
投資の基本原則の一つが「分散投資」です。
複数の銘柄に投資することでリスクを分散し、安定した運用を目指すのが一般的な考え方です。
しかし、ミニ株では資金が限られているため、十分な分散投資を行うのが困難です。
例えば10万円の資金で10銘柄に分散投資しようとすると、1銘柄あたりわずか1万円。
これでは手数料負けしてしまう可能性が高くなります。
また、少額ずつ複数の銘柄を購入すると、それぞれに手数料がかかるため、総コストがさらに高くなってしまいます。
結果として、分散投資のメリットよりもコストのデメリットの方が大きくなってしまうのです。
真の分散投資を行うには、ある程度まとまった資金が必要です。

編集部
少額投資で分散効果を得たいなら、後ほど紹介する投資信託やETFの方が適していると言えるでしょう。
ミニ株のメリットとデメリット

ここまでデメリット面を中心に説明してきましたが、公平性を保つためにミニ株のメリットも整理してみましょう。

編集部
ミニ株の主なメリットは以下の通りです。
- 少額から株式投資を始められる
- 投資の勉強や練習に適している
- 高額株式にも手が届く
- 積立感覚で投資できる
- 配当は受け取れる
一方、デメリットは
- 手数料が割高
- リアルタイム取引ができない
- 指値注文に制限がある
- 株主優待が受けにくい
- 流動性が低い
- 分散投資の効果が薄い
- 大きな利益を期待しにくい
こうして比較してみると、メリットよりもデメリットの方が投資成果に与える影響が大きいことが分かります。
初心者がミニ株で失敗しやすい注意点

投資初心者がミニ株を始める際に陥りがちな失敗パターンがあります。
これらを事前に知っておくことで、同じような失敗を避けることができるでしょう。

編集部
実際の失敗例を交えながら、注意すべきポイントを解説していきます。
小額だからと安易に始めてしまう
1万円程度なら失っても大丈夫でしょ!

という軽い気持ちでミニ株を始める方が多くいますが、これは危険な考え方です。
投資において最も重要なのは、金額の大小ではなく「正しい知識と戦略を持って取り組むこと」です。
小額だからといって適当に始めてしまうと、悪い投資習慣が身についてしまう可能性があります。
例えば、株価チャートの読み方を学ばずに感覚だけで売買を繰り返したり、企業の業績を調べずに人気銘柄に飛びついたりするような行動です。
こうした習慣は、将来より大きな金額で投資する際にも影響してしまいます。
また、ミニ株で小さな利益が出ると「投資は簡単だ」と錯覚してしまい、リスクの高い投資に手を出してしまうケースもあります。
銘柄選びを誤ってしまう
ミニ株初心者によくある失敗が、銘柄選びの誤りです。
「有名な会社だから安心」「株価が安いからお得」といった単純な理由で銘柄を選んでしまうケースが目立ちます。
特に注意が必要なのは、株価の安い銘柄(低位株)への投資です。
株価が安い理由には必ず原因があります。
業績不振、将来性への不安、財務状況の悪化など、様々な要因が株価に反映されているのです。
また、話題性だけで銘柄を選ぶのも危険です。
メディアで注目された銘柄は既に株価が上昇していることが多く、高値掴みをしてしまうリスクが高まります。
正しい銘柄選びには、企業の財務諸表を読み解く力、業界動向の理解、競合他社との比較分析など、幅広い知識が必要です。

編集部
これらの勉強をせずにミニ株を始めても、成果を上げるのは困難でしょう。
手数料を軽く見てしまう
先ほども説明した通り、ミニ株の手数料は投資パフォーマンスに大きな影響を与えます。
しかし、多くの初心者が「数十円程度の手数料なら大したことない」と軽く考えてしまいます。
例えば、毎月1万円ずつミニ株を購入し、手数料が55円かかるとします。
年間の手数料は660円。投資元本12万円に対して0.55%の手数料率です。
20年間続けると、手数料だけで投資元本の10%以上を失うことになってしまいます。
投資の世界では「1%のコスト削減は10%のリターン向上に匹敵する」と言われています。
手数料を軽視することは、将来の資産形成に深刻な影響を与えるのです。
ミニ株の代わりになる!おすすめの投資方法

ミニ株のデメリットを理解したところで、代わりにどんな投資方法があるのでしょうか。

編集部
少額投資のニーズを満たしながら、より効率的な資産形成ができる選択肢をご紹介します。
これらの方法は、コスト面でも分散効果でも、ミニ株を上回るメリットを提供してくれます。
投資信託(インデックスファンド)
ミニ株の代替手段として最もおすすめなのが、投資信託、特にインデックスファンドです。
インデックスファンドは、日経平均株価やTOPIXなどの指数に連動するように運用される投資信託です。
1つの商品で数百から数千の銘柄に分散投資できるため、個別株投資では難しい十分な分散効果を得ることができます。
購入時手数料は無料(ノーロード)のものが多く、信託報酬(運用管理費用)も年0.1%程度と非常に低コストです。
ミニ株の手数料と比較すると、コスト面で圧倒的に有利です。
また、100円から投資できる証券会社も多く、少額投資という点でもミニ株に劣りません。
ETF(上場投資信託)
ETF(Exchange Traded Fund)は、証券取引所に上場している投資信託です。
インデックスファンドと同様に、1つの商品で幅広い分散投資が可能です。
ETFの特徴は、株式と同じように市場でリアルタイム取引できることです。
ミニ株のように決められた時間での取引ではなく、自分のタイミングで売買できます。
運用コストもインデックスファンドと同程度に低く、長期投資に適しています。
ただし、最低投資金額はETFによって異なり、数千円から数万円程度となります。

編集部
ETFは投資信託とミニ株の良いところを併せ持った商品と言えるでしょう。
ある程度投資に慣れてきた方には特におすすめです。
積立NISA・iDeCoの活用
2024年から新しくなったNISA制度や、iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用も検討すべきです。
新NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円まで非課税で投資できます。
iDeCoは掛金が所得控除の対象となるため、所得税・住民税の節税効果もあります。
60歳まで引き出せないという制約はありますが、老後資金の準備には最適な制度です。
これらの制度を活用すれば、ミニ株よりもはるかに効率的な資産形成が可能になります。
税制優遇のメリットは手数料以上に大きな影響を与えるのです。
ロボアドバイザーによる自動運用
投資の知識や時間がない方には、ロボアドバイザーという選択肢もあります。
ロボアドバイザーは、AI技術を使って自動的にポートフォリオを構築・運用してくれるサービスです。
投資家は簡単な質問に答えるだけで、自分に適した投資プランを提案してもらえます。
- ウェルスナビ
- THEO
- 楽ラップなど
手数料は年1%程度とミニ株より高めですが、専門的な運用を任せられるメリットがあります。
完全にお任せできるため、投資初心者でも始めやすく、感情に左右されない機械的な運用により、安定したパフォーマンスが期待できます。
定期預金や社債投資
リスクを抑えたい方には、定期預金や社債投資も選択肢の一つです。
確かに定期預金の金利は低いですが、元本保証されているという安全性があります。
投資に慣れるまでの間、資金の一部を定期預金で保有するのも賢明な判断です。
社債は企業が発行する債券で、株式よりもリスクが低く、定期預金よりも利率が高い特徴があります。
ただし、発行企業の信用リスクがあるため、しっかりとした企業の社債を選ぶことが重要です。

編集部
これらの商品は投資というよりも貯蓄に近い性格ですが、リスク管理の観点から資産の一部に組み入れることを検討してみてください。
ミニ株以外の選択肢を検討する際には、投資信託やETF、FXなどもあります。家計全体のバランスやライフプランを踏まえて資産形成を考えることが重要です。 特にFXにご興味がある方は、以下の情報もチェックしてみてください。
参考:マネーツール –ファイナンシャルプランナー(CFP)が運営するお金のサイト!
ミニ株が向いている人の特徴

これまでミニ株のデメリットを中心に説明してきましたが、全ての人にとってミニ株が不適切というわけではありません。

編集部
以下のような方には、ミニ株が適している場合もあります。
- 投資の勉強や練習として使いたい人
- 特定の企業を応援したい人
- 高額株式を積立で購入したい人
- 投資信託やETFでは物足りない人
まず、投資の勉強や練習として使いたいという方です。
投資信託やETFでは味わえない、個別企業への投資体験を通じて、株式市場の仕組みを学ぶことができます。
失っても問題ない小額で実際の投資を体験することで、将来の本格的な投資に向けた良い準備になるでしょう。
次に、特定の企業を応援したいという方です。
好きな企業や将来性を信じる企業に少額でも投資することで、株主として企業の成長を見守ることができます。
金銭的なリターンよりも、企業への愛着や応援の意味合いが強い場合には、ミニ株は有効な手段と言えます。
また、高額株式を積立で購入したいという方にも適しています。
例えば、株価が数十万円する企業の株式を、毎月少しずつ積み立てて購入していくような使い方です。
ただしこの場合も、手数料の負担は十分に検討する必要があります。
最後に、投資信託やETFでは物足りないという方です。
既に投資経験があり、個別株投資にもチャレンジしたいが、まとまった資金はかけられないという場合に、ミニ株が選択肢となることがあります。

編集部
単に「少額から始められるから」という理由だけでミニ株を選ぶのは避けた方が良いでしょう。
ミニ株に関するFAQ

ミニ株について多くの方が抱く疑問にお答えします。
実際によく寄せられる質問を通じて、ミニ株の現実的な側面を理解していただければと思います。

編集部
これらの回答が、皆さんの投資判断の参考になれば幸いです。
Q
ミニ株で大きな利益を得ることは可能ですか?
A
理論的には可能ですが、現実的には困難です。
大きな利益を得るには、株価が大幅に上昇するか、多額の資金を投入する必要があります。
ミニ株では投資額が限られているため、株価が2倍になっても利益は投資元本分しか得られません。
例えば1万円投資して株価が2倍になっても、利益は1万円です。
そこから手数料を差し引くと、実際の手取りはさらに少なくなります。
また、大きな利益を狙って高リスクな銘柄に投資すると、逆に大きな損失を被るリスクも高まります。
本格的な資産形成を目指すなら、ある程度まとまった資金での投資や、コストの安い投資信託・ETFを検討することをおすすめします。
Q
ミニ株はどの証券会社がおすすめですか?
A
ミニ株を利用する場合、手数料の安さと取引の利便性で選ぶのが基本です。
現在、比較的コストが安いのは楽天証券の「かぶミニ®」です。
買付時のスプレッドが無料の時間帯があり、コスト面でのメリットがあります。
また、2024年から指値注文にも対応し、利便性が向上しています。
SBI証券の「S株」も取扱銘柄数が多く、買付手数料が無料という特徴があります。
ただし売却時には手数料がかかるため、頻繁な売買には向きません。
マネックス証券の「ワン株」は買付手数料が無料で、取引時間も比較的長いのが特徴です。
また、前述の通り、コスト面を重視するなら投資信託やETFの方が有利な場合が多いことも忘れないでください。
まとめ

今回は「ミニ株はおすすめしない」という視点から、その理由や注意点について詳しく解説してきました。
ミニ株の主な問題点は、手数料の高さ、取引の制約、分散投資の困難さなど、投資パフォーマンスに直接影響する要素が多いことでした。
特に手数料の負担は、長期的な資産形成において無視できない大きな要因となります。
一方で、投資の学習や特定企業への応援といった明確な目的がある場合には、ミニ株にも一定の価値があることも確認できました。
重要なのは、自分の投資目的を明確にし、それに最適な投資手法を選択することです。
多くの場合、資産形成を目的とするなら、ミニ株よりも投資信託(インデックスファンド)やETF、さらにはNISAやiDeCoといった税制優遇制度の活用の方が効率的です。
これらの選択肢は、コスト面でも分散効果でも、ミニ株を上回るメリットを提供してくれます。
投資を始める際は、商品の特徴やコストを十分に理解し、自分の目的に合った方法を選択することが成功への第一歩となります。

編集部
ミニ株はその選択肢の一つに過ぎません。
より良い投資成果を得るために、幅広い選択肢を検討してみてください。
住宅ローンのお悩みありませんか??

家族に内緒の借金があるけど…バレずに住宅ローン審査を進められる?
シングルマザーで収入が低いけど、住宅ローンは組める?


過去に犯罪歴があるけど、住宅ローン審査は通る?
このような住宅ローンのお悩みは
ローンとおるくん編集部へお気軽にご相談ください!
- 家族に借金がバレずに住宅ローン審査の手続きを進めることができた!
- シングルマザーでも住宅ローン審査が通ってマイホームを購入することができた!
- 過去の事情でマイホームを諦めていたけど、住宅ローンを組むことができた!
住宅ローンを知り尽くしたプロが親身になって
どんなケースでも住宅ローンを通す方法を一緒に考え
ご提案いたします。
★相談料は無料です!
独自のノウハウで住宅ローン審査通過をサポート
\些細なことでも気軽に相談してください/
\お電話からでも相談できます/
朝10時〜18時まで対応(土日祝休み)