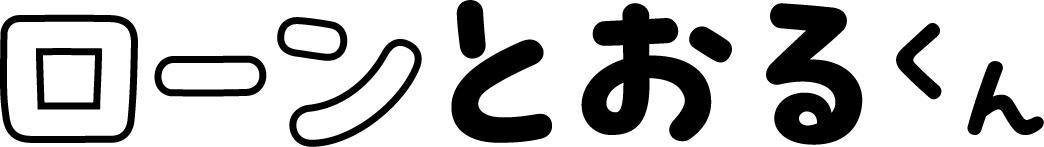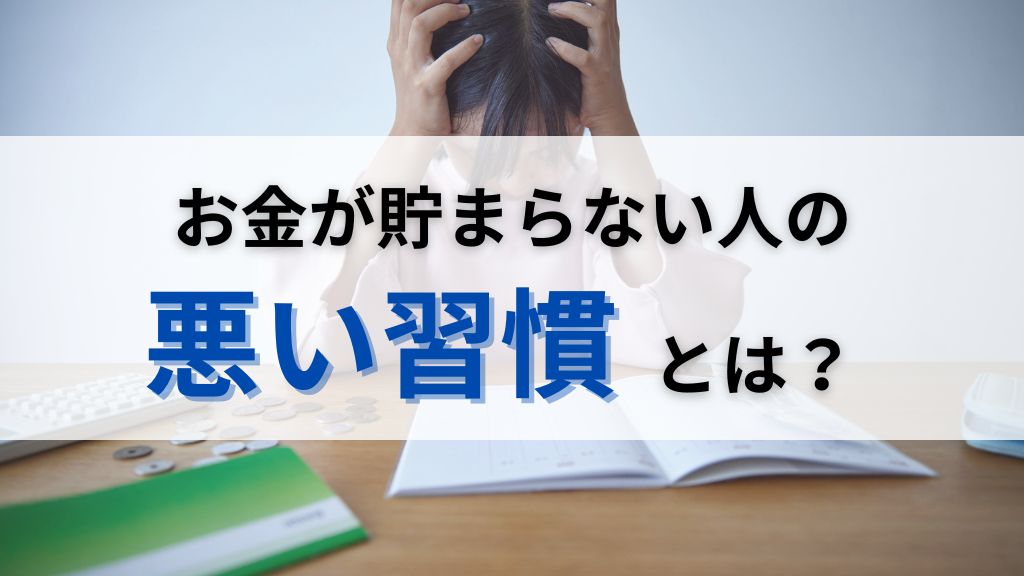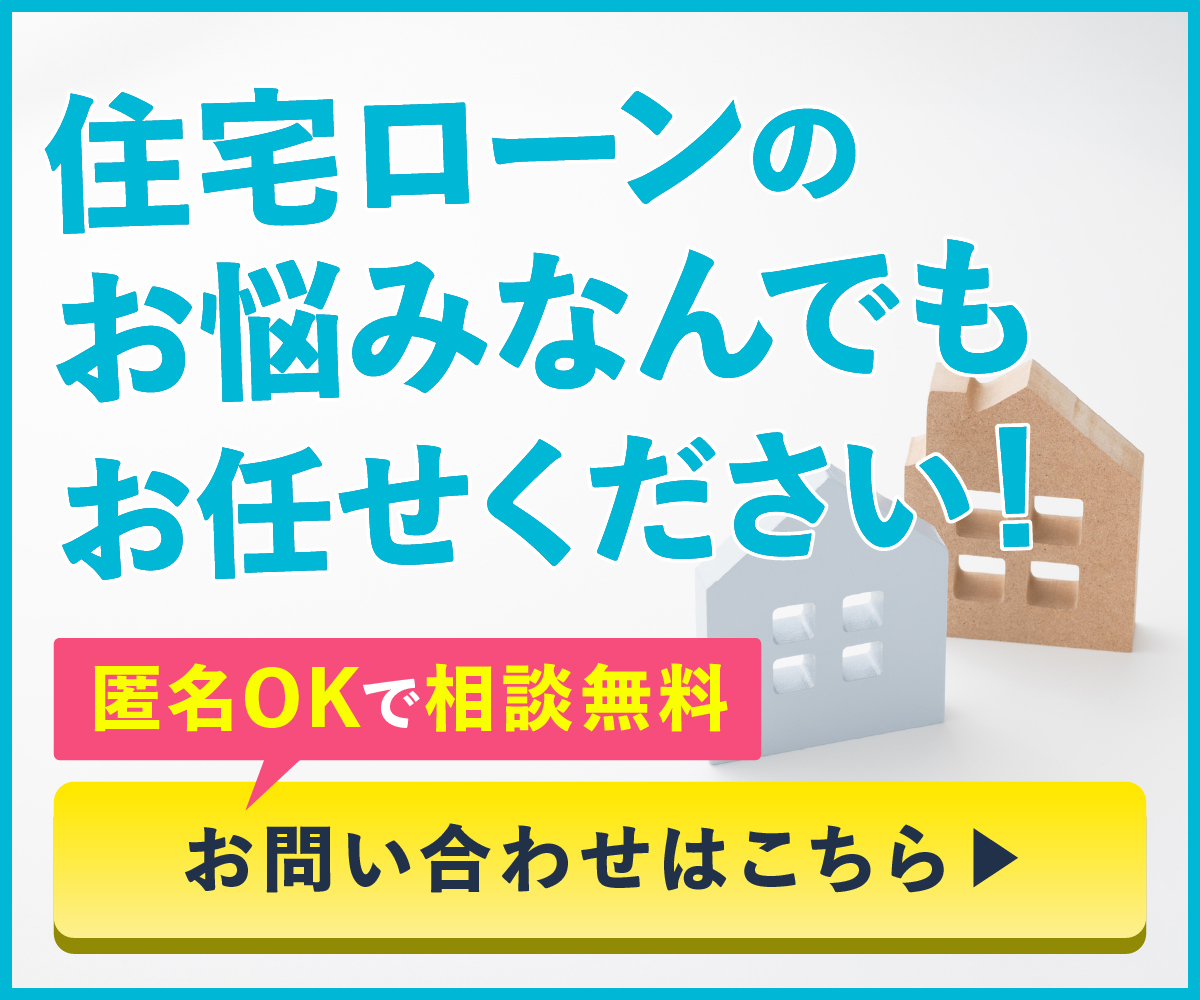なんでお金が貯まらないんだろう?
毎月収入を得ているにもかかわらず、思うように蓄えが増えない状況に直面していませんか?
若いうちからの計画的な資産形成を怠ると、結婚資金・育児費用・住宅購入といった人生の重要な局面で資金不足に陥り、困難な状況を招く可能性があります。
本記事では、お金が貯まらない人の悪い習慣と、お金が貯まりやすくなるポイントをわかりやすく解説します。
- 一般的な貯蓄額の実態
- お金が貯まらない人の悪い習慣
- お金がたまりやすくなるポイント
- 資産形成に役立つ優遇制度の活用法

編集部
さらに、記事後半では新NISA制度やiDeCoなど、資産形成に有利な税制優遇措置についても詳細に解説いたします。
この情報を活用することで、資産形成を妨げる要因を特定し、将来の重要な局面で経済的な選択の幅を広げることが可能になりますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
一般的な貯蓄額の現状を把握する

お金が貯まらない悪い習慣を知る前に、世間の平均的な貯金額を把握しておきましょう。
全体的な傾向を理解することで、個人の資産状況を客観的に評価することができるでしょう。
金融広報中央委員会「家計の金融行動に対する世論調査(令和5年)」を参考に以下の表にまとめました。
二人以上世帯(※1)
| 世帯主の年齢 | 平均値(※2 ) | 中央値(※3) |
|---|---|---|
| 20代 | 249万円 | 30万円 |
| 30代 | 599万円 | 130万円 |
| 40代 | 811万円 | 180万円 |
| 50代 | 1,212万円 | 200万円 |
| 60代 | 1,862万円 | 530万円 |
| 70代 | 1,683万円 | 650万円 |
単身世帯(※1)
| 世帯主の年齢 | 平均値(※2 ) | 中央値(※3) |
|---|---|---|
| 20代 | 121万円 | 9万円 |
| 30代 | 594万円 | 100万円 |
| 40代 | 559万円 | 47万円 |
| 50代 | 1,391万円 | 80万円 |
| 60代 | 1,468万円 | 210万円 |
| 70代 | 1,529万円 | 500万円 |
※1 金融資産を保有していない世帯を含む
※2 預貯金、金銭信託、積立型保険商品(生保・損保)、個人年金保険、債券、株式、投資信託、財形貯蓄、その他金融商品
※3 上位50%と下位50%の境界にいる人の保有額
年代が上がるにつれて金融資産保有額は着実に増加していることがわかります。
特に注目すべきは平均値と中央値の大きな差で、これは一部の高資産者が平均を押し上げている現実を示しています。
20代の中央値が単身世帯で9万円、二人以上世帯で30万円と非常に低いのは、多くの若い世代がまだ貯蓄を始めたばかりであることを表しています。
また、50代以降は単身世帯の方が平均値が高くなる傾向があり、これは世帯人数による支出の違いが影響していると考えられます。
世間の平均額と自分の貯金額を見比べて、自分の貯金額が少なかった人はお金が貯まる習慣を身につけてしっかり資産形成をしていきましょう。
お金が貯まらない人の7つの悪い習慣

ここでは、お金が貯まらない人に共通する7つの悪い習慣を紹介します。
- 家計状況を正確に把握していない
- 貯まる仕組みを整えていない
- 衝動買いが多い
- ボーナスに依存している
- ローンやリボ払いの多用
- 残った分を貯金に回す
- 外食が多い

編集部
悪い習慣がいくつ当てはまっているか一緒にチェックしてみましょう。
家計状況を正確に把握していない
お金が貯まらない人は、家計状況を正確に把握していない人が多いです。
支出を正確に把握し、収入の範囲内で生活を営むことができれば、資産の減少を防ぐことが可能です。
何に過度な支出をしているかを把握することが、効果的な資産形成への第一歩となります。

編集部
不要な支出を特定できなければ、改善すべき点を見つけることはできません。
貯まる仕組みを整えていない
お金が貯まらない人の多くは、「貯めるための仕組み」を持っていません。
仕組みがなければ、月末になる頃には給料を使い切ってしまい、結果的に貯金ができない状態が続いてしまいます。
そこでおすすめなのが、「先取り貯金」の仕組みづくりです。
給料を使う前に貯金分を確保してしまえば、自然とお金は貯まっていきます。具体的には、給与振込先を2つに分ける、または銀行の自動振替サービスを利用して、入金と同時に貯金用口座へ一定額を移す方法があります。
このように自動化すれば、意識せずとも毎月確実にお金が貯まる仕組みが完成します。
衝動買いが多い
衝動買いが多い人は、お金がなかなか貯まりません。
特に「セール」の文字を見ると、つい必要のないものまで購入してしまい、計画性のない支出が増えてしまいます。
買い物をするときは、価格だけで判断するのではなく「自分にとっての価値」で判断することが大切です。たとえ価格が高くても、本当に必要で価値があるものであれば購入しても構いません。しかし、安くても不要で価値のないものなら、買わない方が賢明です。
日頃から「価格」ではなく「価値」で選ぶ習慣を身につけることで、衝動買いを減らし、無駄な出費を防ぐことができます。
ボーナスに依存している
ボーナスに過度に依存した家計管理は、お金が貯まらない人によく見られる習慣です。
「来月ボーナスが入るから、今月は少しくらい使いすぎても大丈夫」という考え方は非常に危険です。
ボーナスは毎年必ず同じ金額が支給されるものではなく、企業の業績や個人の評価によって変動します。そのため、予想より少ない金額しか支給されなかった場合、一気に家計が厳しくなるリスクがあります。
高額な買い物をしたくなる気持ちは理解できますが、ボーナスはできるだけ貯蓄に回し、普段の生活費は月々の給与の範囲でやりくりすることが賢明です。

編集部
ボーナスを受け取ったら、必要な分だけを手元に残し、残りはすべて貯金に回す習慣を身につけましょう。
ローンやリボ払いの多用
高額商品を購入する際に、各種ローンやリボ払いを利用すると、資産形成が困難になるどころか資産が減少していきます。
リボ払いとは利用金額に関係なく、毎月一定金額を返済していく支払い方式です。
例:10万円の商品購入でも毎月の返済は5,000円
月々の返済額が少なくなるのは魅力的ですが、高い利率が設定されており、返済を続けても元本がなかなか減少しません。
また、アコムなどのATMで手軽に利用できるローンも高い利率が設定されているため、利息負担が増大し返済総額が膨らんでいきます。
ローンやリボ払いで高額な利息を支払っていては、資産形成は実現できません。

編集部
既に利用している場合は繰上げ返済などで早期完済を目指し、利息負担を最小限に抑えましょう。
残った分を貯金に回す
月々の収入から自由に支出し、残った分があれば蓄財に回すという方法を採用していませんか?
毎月の収入から生活費や娯楽費などを支払い、余剰分を蓄財に回す方法では、効果的な資産形成は困難です。
手元に資金があると、つい支出してしまうからです。
たとえ残余があっても毎月一定額ではないため、年間でどれだけの蓄財ができるか予測が立てられません。
そこで収入を得た時点で蓄財分を先に別口座に移動させておく方法がおすすめです。
先に資金を移動させることで支出の歯止めがかかり、年間蓄財額も明確になるため計画も立てやすくなります。

編集部
金融機関の自動振替サービスを活用すれば毎月自動的に別口座に移転でき、非常に便利です。
外食が多い
お金が貯まらない人は外食やデリバリーサービスの利用が多い傾向があります。
確かに自炊は手間がかかり、仕事から帰宅後の調理は負担になります。
しかし、外食やデリバリーサービスは自炊と比較して支出が増加します。
月に数回程度の利用であれば問題ありませんが、面倒だから、楽をしたいからという理由で頻繁に利用するのは避けるべきです。
どうしても調理が困難な人は宅配食サービスを利用すれば支出を抑えることができます。

編集部
宅配食サービスなら、料金が手頃でメニューが充実しているYOSIKEIがおすすめです。
お金が貯まりやすくなる4つポイント

お金が貯まらない悪い習慣を紹介しましたが、効果的な蓄財を実現するにはどのような行動を取れば良いでしょうか?
ここではお金が貯まりやすくなる4つの行動を紹介します。
- 家計簿をつける
- 定期的な固定費の見直し
- 先取り貯金をする
- 資産運用
これらを実践していけばお金が貯まりやすくなります。
家計簿をつける
自分の資産状況を正確に把握するためには、家計簿をつけることをおすすめします。
- 自分の資産状況を明確に把握できる
- 何にいくら使ったのかを把握できる
- 計画的に貯金を進められる
それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
自分の資産状況を明確に把握できる
家計簿をつけることで、自分の資産状況を数字で正確に把握できるようになります。
これまで「なんとなくお金が貯まっていない」と感じていたことも、記録することで明確な数値として可視化されます。
給料は明細を見ればすぐに確認できますが、支出は家計簿をつけなければ正確にはわかりません。
支出額が明確になれば、収入から差し引いて、毎月いくら貯まっているのか、あるいはいくら不足しているのかを把握できます。
具体的な数字がわかれば、足りない分を支出から減らすだけで改善が可能です。

編集部
毎月の家計状況を把握することこそが、お金が貯まる家計づくりの第一歩です。
何にいくら使ったのかを把握できる
お金が貯まらない人の多くは、自分が何にいくら使っているのかを正確に把握していません。
家計簿をつければ、毎月の支出内容と金額が明確になり、不要な支出をすぐに見つけられます。
やみくもに節約するのではなく、無駄な支出だけを減らすことが、ストレスを感じにくい家計改善のポイントです。

編集部
支出を細かく見直すことで、解約し忘れていたサブスクサービスなど、意外な無駄が発見できる場合もあります。
計画的に貯金を進められる
家計簿で資産状況やお金の流れを把握できれば、毎月どれくらい貯金できるかを具体的に見積もることができ、貯金の習慣が身につきやすくなります。
資産状況を把握せずに勘だけで設定した貯金額は、無理が生じやすく長続きしません。
毎月の貯金計画を立てれば、年間でどの程度貯まるのかも明確になり、子どもの教育費など将来の大きな支出にも備えやすくなります。

編集部
将来に備えるためには、無理のない計画的な貯金が大切です。
定期的な固定費の見直し
定期的な固定費の見直しで無駄な支出を減らせます。
- 保険料金
- スマホの料金
- ガス・電気料金
保険料金
お金がなかなか貯まらない原因のひとつに、必要以上に多くの保険に加入してしまい、いわゆる「保険貧乏」になっているケースがあります。
加入している保険が本当に必要かどうかは、定期的に見直すことが大切です。
例えば、子どもが成長すれば高額な保障が不要になることもあり、ライフステージに応じて必要な保険は変化します。
周囲が入っているからという理由だけで安易に加入するのは避けましょう。

編集部
毎月数万円の保険料を支払っている場合は、早めの見直しをおすすめします。
スマホの料金
いまや生活必需品となったスマートフォンですが、高額な大手キャリアのプランをそのまま契約していませんか?
現在では、ahamoやpovoなど、大手キャリアとほぼ同等の回線品質で利用できる格安SIMが数多く登場しています。

編集部
格安SIMとは、大手キャリアの料金プランと比べて低価格で利用できるSIMカードのことです。
例えば、docomoからahamoへ切り替える場合、月額料金が7,315円から2,790円へ下がり、月々4,525円もの節約になるケースもあります。
携帯会社の乗り換えは大変と思うかもしれませんが、手続きは1時間程度で乗り換えが可能です。
また、2022年4月には携帯の契約期間の縛りが撤廃されたので、高額な違約金を払う必要もなくなりました。

編集部
大手キャリアで契約している人は1度料金をシュミレーションしてみましょう。
ガス・電気料金
ここ数年のガス・電気料金の値上げは、家計に大きな負担を与えています。
日常的にこまめに電気を消したり、コンセントからプラグを抜いたりして節約していても、契約会社を見直すことでさらに大きな節約ができる可能性があります。
ガスは2017年、電気は2016年から自由化されており、利用する会社を自由に選べます。
ガスと電気を同じ会社にまとめたり、携帯会社とセット契約にすることで割引が適用されるお得なプランも多く、一度見積もりを取って比較してみる価値があります。
「エネチェンジ」などの比較サイトを使えば、複数の会社の料金を一括で確認でき、1社ずつ調べる手間もかかりません。
また、大手以外の会社を選んでも品質が落ちる心配はなく、ガスや電気はこれまでと同じ仕組みで供給されます。

編集部
契約変更に複雑な手続きや工事は不要な場合がほとんどです。一度シミュレーションして、節約効果を確かめてみましょう。
先取り貯金をする
お金が貯まらない人は、毎月の給料を自由に使い、余った分だけを貯金に回す傾向があります。
しかし、この方法では口座の残高をつい使ってしまい、月末には貯金に回せるお金が残らないことも少なくありません。
一方で、お金が貯まる人は給料が振り込まれた時点で、あらかじめ決めた貯金額を別口座へ移し、残った金額で生活します。
銀行によっては毎月自動で指定額を振替できるサービスもあるため、こうした仕組みを活用すれば無理なく貯金を継続できます。

編集部
先に貯金分を確保することで、使いすぎを防ぎ、確実にお金を貯められます。
資産運用
お金が貯まる人は、貯金を銀行口座に預けるだけでなく、株式・債券・不動産・投資信託などに分散投資して資産を増やしています。
資産運用には必ずリスクが伴いますが、長期的かつ分散された投資を行うことで、リスクを抑えながら資産形成を進めることが可能です。
一般的に、株式はリスクが高く、債券はリスクが低いとされています。
そのため、リスクの高い資産と低い資産をバランスよく組み合わせ、長期的に運用することが重要です。

編集部
国内株式だけでなく海外株式にも投資するなど、投資先の地域も分散しておくと安心です。
お金を貯めるために有効な3つの優遇制度を解説

続いて、お金を貯めるために有効な3つの優遇制度について解説します。
- 財形貯蓄
- NISA
- iDeCo
税金で有利になるものもあるため、それぞれ解説していきます。
財形貯蓄
財形貯蓄は、給与の一部を毎月一定額、自動的に積み立てる制度です。
多くの場合、企業が福利厚生の一環として導入しており、給与から天引きされるため、自分で振り替える手間がありません。
金利は低く、大きく増やすことはできませんが、「ついお金を使ってしまう人」や「貯蓄の習慣がない人」にとっては、確実に貯められる有効な方法です。

編集部
会社による自動的な先取り貯金制度です。
NISA
NISA(ニーサ)とは、「少額投資非課税制度」のことで、個人投資家向けの税制優遇措置です。
株式や投資信託などの運用で得られた利益や配当が、非課税となります。
2024年からは制度が大幅に拡充され、非課税期間が無期限となり、年間投資枠や生涯投資枠が設定されました。
NISAには2つの投資枠があり、それぞれを組み合わせて年間最大360万円まで投資可能です。
| 投資枠 | 主な投資対象 | 年間投資上限額 | 非課税期間 |
|---|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 長期・積立・分散投資に適した投資信託 | 120万円 | 無期限 |
| 成長投資枠 | 上場株式・ETF・REIT・投資信託など幅広く投資可能 | 240万円 | 無期限 |

編集部
これから投資を始める人は、少額から長期でコツコツ積み立てられる「つみたて投資枠」から始めるのがおすすめです。
つみたて投資枠には以下のようなメリットが4つあります。
- 非課税で長期運用できる
- 少額から投資を始められる
- 金融庁が選定した低コスト・優良ファンドのみ
- 自動積立でタイミングに悩まない
非課税で長期運用できる
運用益や分配金が非課税で、保有期間に制限はありません。
売却しない限り、ずっと非課税で資産を運用できます。長期的な資産形成に向いており、複利効果を最大限活かせます。
少額から投資を始められる
つみたて投資枠は、金融機関によっては100円から投資可能です。
大きな初期資金がなくても、無理のない金額でスタートできます。少額からでもコツコツ積み立てることで、長期投資による複利の力を享受できます。
金融庁が選定した低コスト・優良ファンドのみ
つみたて投資枠で選べる投資信託は、金融庁が基準を設けて厳選した低コスト・長期投資向けの商品ばかりです。
初心者でも安心して選べる優良ファンドが揃っており、長期で積み立てる際のコスト負担を抑えられます。
自動積立でタイミングに悩まない
通常の投資では「いつ買うか」を判断する必要がありますが、つみたて投資枠では毎月や毎週など、あらかじめ決めたタイミングで一定額を自動的に投資できます。
そのため、市場の上下に振り回されず、計画的に投資を継続できます。
この積立方式は「ドルコスト平均法」と呼ばれ、価格が高いときには少なく、安いときには多くの口数を購入する仕組みです。
一定額を定期的に投資し価格変動リスクを分散させる方法
結果として購入単価が平準化され、価格変動リスクの軽減につながります。
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、投資信託や定期預金などで運用して老後資金を準備する制度です。
- 掛金が全額所得控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながる
- 運用益が非課税
- 受け取るときも一定の税優遇を受けられる
注意点は、原則60歳まで引き出しができないため、長期的な資金拘束がある点です。
そのため、老後資金作りには非常に有効ですが、60歳以前に使う予定のお金を貯めるには向いていません。
短・中期の資産形成には、新NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)の活用がおすすめです。

編集部
まずはNISAを活用し、それでも資金に余裕があればiDeCoを併用しましょう。まだNISAやiDeCoを始めていない方や証券口座を持っていない方には、手数料が低く取扱商品が豊富な「SBI証券」が人気です。
お金が貯まらない人に関してよくある質問

お金が貯まらない人に関するよくある質問をまとめました。
1年で100万円貯めるには月いくら貯めればいい?
1年間で100万円の蓄財を実現するためには毎月平均8.4万円を貯金する必要があります。
収入の3割を貯蓄するのが一般的であることを考慮すると、毎月8.4万円を貯金するには約28万円の収入が必要です。
お金が貯まらない人の共通点は?
お金が貯まらない人には以下の共通点が見られます。
- 家計状況を正確に把握していない
- 貯まる仕組みを整えていない
- 衝動買いが多い
- ボーナスに依存している
- ローンやリボ払いの多用
- 残った分を貯金に回す
- 外食が多い
該当する人は注意が必要です。
お金が貯まらない夫婦の特徴とは?
互いの収入や支出を把握しようとせず、家計管理を一方に完全に委ねている場合が多いです。
一方で、夫婦で資産についてよく話し合っている家庭は資産が蓄積されていきます。
貯金がうまくいかない時のストレスをどうすればいい?
お金がうまく貯まらない時のストレスは以下のような方法で対処しましょう。
- 運動による気分転換
- 十分な睡眠の確保
- 他人との貯蓄額比較の回避
特に他人との蓄財額比較でストレスを蓄積するのは時間の無駄です。
SNSなどで他人の充実した生活を見ることを控えるとストレスから解放されます。
まとめ|悪い習慣を見直して効果的な資産形成を実現しよう

本記事ではお金が貯まらない人の悪い習慣を紹介しました。
- 家計状況を正確に把握していない
- 貯まる仕組みを整えていない
- 衝動買いが多い
- ボーナスに依存している
- ローンやリボ払いの多用
- 残った分を貯金に回す
- 外食が多い
自分に当てはまっている悪い習慣はありましたか?該当する行動がある場合はただちに見直しましょう。
また、資産形成に有効な優遇制度も3つ紹介しました。
- 財形貯蓄
- NISA
- iDeCo
これから資産形成を開始する人は財形貯蓄、資産が蓄積されてきたら「NISA」、「iDeCo」を活用して、税制面で有利な資産形成を開始しましょう。
今回は個人向けにご案内しましたが、法人で特に医療美容の場合、プロのマーケティングを付けるのも一つの方法です。安心して資金形成ができる土台作りに役立ちます。
ロロント株式会社は、美容医療に特化したWeb集客支援を強みとし、SNS、SEO・LP制作・アフィリエイトなど成果に直結する戦略設計を提供しています。AIとSNSを活用したマーケティング支援に加え、オンライン診療やインフルエンサーを活用した支援の他、稼ぐ力を鍛える自社メディアロロメディアの運営も行っています。
住宅ローンのお悩みありませんか??

家族に内緒の借金があるけど…バレずに住宅ローン審査を進められる?
シングルマザーで収入が低いけど、住宅ローンは組める?


過去に犯罪歴があるけど、住宅ローン審査は通る?
このような住宅ローンのお悩みは
ローンとおるくん編集部へお気軽にご相談ください!
- 家族に借金がバレずに住宅ローン審査の手続きを進めることができた!
- シングルマザーでも住宅ローン審査が通ってマイホームを購入することができた!
- 過去の事情でマイホームを諦めていたけど、住宅ローンを組むことができた!
住宅ローンを知り尽くしたプロが親身になって
どんなケースでも住宅ローンを通す方法を一緒に考え
ご提案いたします。
★相談料は無料です!
独自のノウハウで住宅ローン審査通過をサポート
\些細なことでも気軽に相談してください/
\お電話からでも相談できます/
朝10時〜18時まで対応(土日祝休み)